 三つ峠の三十三観音は、いつ設置されたのか?
三つ峠の三十三観音は、いつ設置されたのか?八十八大師は、八十八体供養塔の年代と同じと考えることにする。
すると三十三観音は、それ以前か以後なのか?
明治直前だと思うのだが、そうなると奉納者と三つ峠の関係に疑問が発生する。
空胎上人とその一門たちは、三つ峠をどのようにしたかったのだろう。
空胎上人以前の信仰と、新事業とは何ら問題はなかったのか?
33ヶ所巡りの事業は、成功したのだろうか?
三つ峠の竜馬伝、篤姫、新撰組。 三つ峠山中には、別世界があったのだろうか?
里ではペリー来航の影響で、お台場建設に協力していた時代のこと。

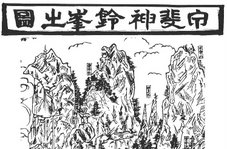





0 件のコメント:
コメントを投稿