 三つ峠が三つ峠の形であるのは、
三つ峠が三つ峠の形であるのは、下暮地登山道からの眺めでしかない。
上暮地側から三つ峠を眺めても
もう見栄えが変わってしまう。
手前の山は方位磁石が狂うことのない
『金峰山(きんぼうやま)』。
ちょうど金峰山の頂上の向こう側が
だるま石のあるところ。
中央から真上延びる尾根が登山道である。
左に延びる稜線は、東の尾根。 大ダルの弧が美しい。 東沢をはさみ右側から上に伸びる尾根。
この尾根の頂上を『大久保山』とする登山地図がある。 前に述べたが、そこをそう呼ぶことを
地元住民は全く知らない。 東沢と俵石の頂上だけなのである。
山に登ると、登った山が見えない。 山を見るには、山に登らないことになる。
やはり、三つ峠を見るには山祗神社から歩く必要がある。
なぜあの場所にだるま石があるかと思うと、やはりあの場所である必要があるという気がする。
三つ峠は、その姿が美しいのだと思う。
今不思議に思うのは八十八大師の奉納者が大幡方面の方なのだが、
彼らは東の尾根を歩いたのだろうかという疑問。
下暮地と大幡は、仏の沢、湯ノ沢を通じてつながっていた。
だるま石を通過する必要がある気もする。

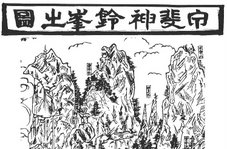





0 件のコメント:
コメントを投稿